「きゃーっ。誰か助けて」
「怪人が襲ってきたぞー。逃げるんだ」
都内の一角に突然現れた悪の組織。歯に食べかすが挟まったかのようなシーシーと奇怪な音を発する黒ずくめの者達が、住民たちを威嚇する。悪の集団の真ん中にはひと際立派な鼻を携えた、まるでマンモスのような大男が偉そうに腕を組み、仁王立ちをしていた。
「お前たち。好きに暴れるがよい。このきれいな街並みを黒く汚してしまえ」
少し前に再開発が終わり、以前とは比較にならないほど立派になった駅前の広場。まだガムひとつこびりついていない整って敷かれた白いタイル。木目が鮮やかなベンチ。青々と茂った樹木。穏やかな風景がピンチを迎えていた。
「ふははははは。お前たちの野望はいま砕かれる」
「なんだと! 誰だ私の邪魔をするやつは」
声の主は広場の真ん中に建てられたかぼちゃの馬車の銅像にぴんと背筋を伸ばし、怪人たちを見下ろしている。
「ワクドキハピラブカンパニー所属。ワクドキレッド」
「ワクドキパープル」
「ワクドキピンク」
「でたなシャイン戦隊! 今日こそお前たちを倒してやる」
「悪に滅ぶ正義はない! いくぞ怪人ども」
昼の三時。買い物客と下校帰りの学生が賑わうなか。正義と悪の戦いが幕を開ける。
「えー。では、これから今日の反省会をしたいと思います」
立川駅から徒歩ニ十分圏内にある古い社屋の一室。戦いを終えたシャイン戦士達はところどころ錆のあるステンレス製の長テーブルを囲う形で座っていた。
はいっ。普段めったに発言しないパープルが我先にと手をあげた。
「おおっ。パープル。君もやっとやる気に……」
「いや帰ります」
「何を言ってるんだ。まだ会議は始まったばかりだ」
「なんでこんな臭い恰好で会議しなきゃなんないのよ」
怪人との戦いは熾烈なもので、互いに一進一退の攻防を繰り返していたが、怪人は放った黒い鼻水の攻撃が全てを終わらせた。シャイン戦士だけではなく、戦いを観戦していた地域の住人にも被害を及ぼしたそれは触れたが最後。酷い悪臭と汚れ、拭き取ろうにも驚異的な粘り気によって妨害された。
結果、怪人以外の全員からの非難、罵倒によって悪の組織は窮地に陥り、頭を下げながらすごすごと退場していってしまった。
戦いに勝利したはずの戦士達は、僅かな慰みの拍手をもらいながらその場を後にし。乗ってきたおんぼろ社用車に揺られながら、こうして作戦会議室に戻ってきた。
「ほんと最悪。シャワーもないし。ありえない」
「おちつけよパープル」
「やめてよその呼び方」
「??。……紫音」
「苗字で呼びなさいよ! 中野さんって!」
「そんなの。全然ヒーローぽくないじゃないか」
「私も色で呼べれるのは嫌かな」
「なっ。ピンクまでそんな」
「二対一で決まり。今の世の中数が正義よ。わかった? 佐藤さん」
「やめろ! その名前で呼ぶのは。俺の名前はワクドキレッド。悪の組織から地球を守る──」
「佐藤君無理だって。胸元の社員証に『佐藤晤郎』て書いてあるんだから」
「違う。俺は、俺は」
突然けたたましいサイレンが部屋中に響き渡る。
「緊急事態発生。緊急事態発生。東京都○△市■■町四つ角商店街にて怪人の発生を確認。シャイン戦士達は至急現場に急行せよ」
部屋の中央に置かれたスピーカーから助けを求める声。佐藤は椅子から即座に立ちあがった。
「二人とも出動要請だいくぞ!」
「そうね。もういこっ」
「お疲れ様でしたー」
部屋にある壁掛け時計は午後の五時。定時を指している。
「二人とも待ってくれよ」
「正義の味方なら。定時くらい守りなさいよ。時間も守れない人が誰かを救うなんてできないわよ」
「ごめんね、佐藤君。私も帰るからお疲れ様。頑張ってきてね」
静寂が狭い室内を包み込む。
ガチャリッ。佐藤の背後で再び扉が開く音が聞こえる。
「やっぱり戻ってきてくれたのか二人とも」
佐藤の期待とは裏腹に、視界に映るのは立派に禿げ上がった頭部が目印の戦隊課の肌見課長。
「佐藤君。緊急要請が入ったようだね」
「はいっ。戦隊課のリーダーとして職務を全うっ」
「いい。そういうの本当にいいから。行きたければ勝手に行ってきなさい。ただし、残業代出さないから! あと、私服で行ってね。じゃあね、私帰るから」
再び部屋に静寂が訪れる。部屋のスピーカーからは救助要請の音声が延々と流れ続けていた。
この表現しようのない寂しさはなんなのか。佐藤は零れ落ちそうになる涙をぐっとこらえ、部屋を出た。上司の命令は絶対だ。着替えをしなくてはいけない。この着ているスーツを脱いだらただのおじさんじゃないのか? そんなことも頭をよぎったが。佐藤は止まらない。これは彼がヒーローであるからだ。
「おっ、佐藤いたいた。悪いけど今から飲みいくぞ」
「……いいですね。いきましょう先輩!」
佐藤はお世話になっている先輩の誘いは断らない。これは彼がサラリーマンだから。自分が真のヒーローになる日はくるのか。夕焼けがまちを紅く染め上げていくのを尻目に、赤提灯が連なる路地に佐藤はそっと溶け込んでいく。その背中はどこか寂しげであった。
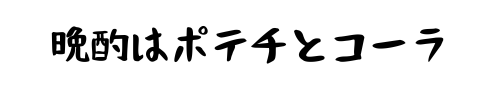



コメント